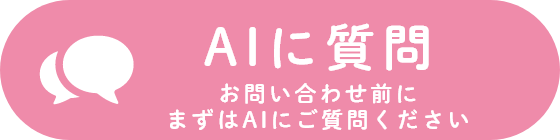月経異常とは、月経の経血量が多かったり周期が不安定だったり、正常ではない月経パターンのことです。
月経異常には月経不順や過多月経、無月経、月経前症候群(PMS)などさまざまな症状があります。
この記事では、月経異常が起こる原因について詳しく解説します。
月経異常の症状や治療方法もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
月経異常でみられる症状

月経異常でみられる症状には以下のようなものがあります。
- 月経困難症
- 月経前症候群(PMS)
- 月経前不快気分障害(PMDD)
- 月経不順
- 過多月経
- 無月経
ここでは上記の6つの症状についてそれぞれ解説します。
月経困難症
月経の際に現れる症状には腹痛、腰痛、頭痛などがありますが、通常はこれらの症状が出ても軽度です。
日常生活に支障が出る程強い症状が出る状態は『月経困難症』と呼ばれます。
月経困難症には『機能性月経困難症』と『器質性月経困難症』の2種類あり、それぞれ以下のような特徴があります。
| タイプ | 特徴 | 症状の原因 |
| 機能性月経困難症 | 身体に問題となる疾患がなくても現れる | 強い子宮の収縮 |
| 器質性月経困難症 | 身体にある疾患が原因で引き起こされる | 子宮内膜症や子宮腺筋症、子宮筋腫などの疾患 |
器質性月経困難症の原因となる疾患は、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症などです。
原因となる疾患を治療することで、生理痛の症状の緩和が期待できます。
月経前症候群(PMS)
月経前症候群(PMS)は、月経が始まる3日〜10日前に身体的または精神的な症状が現れるものです。
原因は女性ホルモンの一種であるプロゲステロンの過剰分泌と考えられています。
月経前症候群の代表的な症状は以下の通りです。
- 頭痛や偏頭痛
- 腰痛
- 便秘や下痢
- 手足のむくみ
- イライラ
- 抑うつ状態
- 集中力の低下
- 不眠や過眠
- 過食など
月経前症候群(PMS)の症状は人それぞれで、200種類以上あるともいわれており、中には日常生活に支障が出るほど強い症状が出る場合もあります。
月経前不快気分障害(PMDD)
月経前不快気分障害(PMDD)は、月経前症候群(PMS)と同様、月経前3日〜10日にかけて症状が出るものです。
月経前症候群(PMS)の症状のうち、精神的な症状が悪化した場合に月経前不快気分障害(PMDD)と診断されます。
イライラや抑うつ状態などの感情のコントロールが難しくなるのが特徴で、月経が始まると症状が落ち着きます。
原因は女性ホルモンのプロゲステロンの分泌量が関係している場合だけでなく、心療内科の疾患が関係している場合が考えられるため、原因を特定することが大切です。
月経不順
月経不順は月経周期に異常が生じている状態のことです。
月経周期とは、月経の開始日から次の月経の開始日の前日までの期間の長さのことで、正常な月経周期は25日〜38日の間となっています。
この月経周期よりも短かったり長かったりする場合、月経不順と診断されます。
月経不順には『希発月経』と『頻発月経』の2種類があり、それぞれの診断基準は以下の通りです。
| 月経周期 | 頻度 | |
| 希発月経 | 39日以上 | 少ない |
| 頻発月経 | 24日以内 | 多い |
思春期や更年期はホルモンバランスの乱れによって月経不順が引き起こされやすい傾向にありますが、成熟女性で月経周期の異常が続く場合は注意が必要です。
体に何らかの問題がある可能性も考えられるため、早めに婦人科を受診しましょう。
過多月経
過多月経は正常な月経と比べて、経血量が多くなってしまう状態のことです。
正常な月経の経血量は1回の生理中に20〜140mlの範囲内とされ、多い日でも2〜3時間に1回程度の頻度でナプキンを交換する程度です。
以下のような状態の場合、過多月経に分類されます。
- 昼でも夜用ナプキンを使う日が3日以上ある
- 1時間に1枚以上のペースでナプキンを消化する
- 以前よりも月経量が増えた
過多月経になると鉄欠乏性貧血に陥る場合があり、以下のような症状が現れることがあります。
- 頭痛
- 動悸や息切れ
- 倦怠感
- めまい
- 耳鳴りなど
症状が重い場合は、黄体ホルモン放出子宮内リングや子宮膜焼灼術、子宮摘出術などの手術を行う場合があります。
無月経
無月経は月経が来ない状態のことで、『続発性無月経』と『原発性無月経』の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 原因 |
| 続発性無月経 | それまであった月経が3か月以上停止している状態 | 過度のダイエット、肥満、ストレス、環境の変化などによる女性ホルモンバランスの乱れ |
| 原発性無月経 | 18歳を迎えても初経が来ない状態 | 染色体異常や子宮・卵巣の発育障害 |
無月経を引き起こす原因はさまざまなため、受診して原因を特定することが大切です。
月経異常が起こる原因・メカニズム

月経異常が起こる原因には以下のようなものがあります。
- 精神的・身体的ストレスによる女性ホルモンバランスの乱れ
- 思春期・更年期によるもの
- 病気の影響
ここでは上記の原因についてそれぞれ解説します。
精神的・身体的ストレスによる女性ホルモンバランスの乱れ
月経異常は、ホルモンバランスの乱れが原因で引き起こされることが多いです。
ホルモンバランスが乱れる原因には以下のようなものがあります。
- 仕事や人間関係による精神的ストレス・疲労
- 無理なダイエットによる栄養不足
- 体の冷え
- 加齢
生活習慣の乱れによってホルモンバランスが崩れることもあるため、月経異常を予防するためには生活習慣の見直しが大切です。
思春期・更年期によるもの
思春期や更年期は月経異常が起こりやすい傾向にあります。
思春期は性機能がまだ十分に完成していないため、月経の不調や不順が起こりやすいです。
思春期は8~9歳ごろから始まりますが、性機能や生殖能力が十分に成熟するまでには10年程度の期間を要します。
この時期は月経異常が起こりやすいため過度に心配する必要はありません。
ただし症状がひどく、回を重ねるたびに症状が重くなっていく場合は、病気の可能性が考えられるため早めに婦人科を受診しましょう。
また更年期に月経異常が起こりやすい理由は、女性ホルモンを分泌していた卵巣の機能が衰えてくるためです。
卵巣機能が衰えることでホルモンの分泌が不安定な状態となり、月経異常が引き起こされます。
病気の影響
身体にある病気が原因となり、月経異常が起こっている可能性もあります。
月経異常と原因となり得る病気としては、子宮筋腫や子宮内膜症、子宮腺筋症などが挙げられます。
これらの病気が原因で月経異常が引き起こされている場合、原因となっている病気の治療が必要です。
月経異常の原因と考えられる病気は次の見出しで詳しく解説します。
月経異常の原因と考えられる病気
月経異常の原因と考えられる病気には以下のようなものがあります。
- 子宮筋腫
- 子宮内膜症
- 子宮腺筋症
- 卵巣腫瘍
- 子宮体がん
- 子宮頸がん
- 多嚢胞性卵巣症候群
ここでは上記8つの病気についてそれぞれ解説します。
子宮筋腫
子宮筋腫は子宮に腫瘍ができる病気です。
女性ホルモンの一種であるエストロゲンが大きく関わっており、子宮筋腫になると以下のような症状が現れます。
- 過多月経
- 月経痛
- 腹痛
- 貧血
- 頻尿
- 便秘や下痢
月経中は筋腫が大きくなるため、腹痛や腰痛などの生理痛が強く現れやすくなります。
閉経すると症状が軽くなり、筋腫も小さくなるのが特徴です。
子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮内腔にある子宮内膜が卵巣や卵管などに発生してしまう病気です。
卵巣にできた子宮内膜は卵巣チョコレート嚢腫と呼ばれ、大きさや年齢により卵巣がんのリスクが上昇します。
子宮内膜症の主な症状は以下の通りです。
- 月経痛
- 腰痛
- 排便痛
- 性交痛
投薬治療と手術による治療がありますが、どちらの治療法も再発のリスクが高いため、長期の経過観察が必要となります。
子宮腺筋症
子宮腺筋症は、子宮内膜の組織が子宮の筋肉の中に入り込んでしまう病気です。
症状が進行すると子宮の膜が大きくなるため、似たような症状の子宮筋腫との鑑別が必要になります。
子宮腺筋症の主な症状は以下の通りです。
- 月経痛
- 過多月経
- 貧血
- 骨盤痛
出産経験のある30代後半〜40代の女性に多い病気ですが、妊娠経験のない20歳代でも発症することがあります。
卵巣腫瘍
卵巣腫瘍は、卵巣に腫瘍ができる病気です。
発生場所によって表層上皮性・間質性腫瘍、性索間質性腫瘍、胚細胞腫瘍の大きく3種類に分けられます。
卵巣腫瘍の主な症状は以下の通りです。
- 下腹部痛
- 腹部膨満感
- 頻尿
腫瘍が破裂したりお腹の中でねじれたりすると、突然強い下腹部痛が起こることもあります。
治療方法は手術療法が原則となり、悪性腫瘍の場合は術後に抗がん剤による治療が必要です。
子宮体がん
子宮体がんは、子宮自体に悪性腫瘍ができる病気です。
子宮体がんの発生には女性ホルモンのエストロゲンが深くかかわっており、子宮内膜増殖症という疾患を経て子宮体がんが発生します。
出産経験のない方や肥満の型、月経不順のある方などに多い病気となっています。
子宮体がんの患者様に多い自覚症状は不正出血で、50〜60歳代に発症する方が多いです。
子宮頸がん
子宮頸がんは、子宮の入り口部分に悪性腫瘍ができる病気です。
主な原因はHPV(ヒトパピウローマウイルス)の感染で、性的接触により感染します。
子宮頸がんには主に以下のような症状があります。
- 不正性器出血
- おりもの
- 性行為の際の出血
- 下腹部痛
初期段階ではほとんど自覚症状がないため、検診を定期的に受けることで早期発見・早期治療に努めることが大切です。
多嚢胞性卵巣症候群
多嚢胞性卵巣症候群は、両側の卵巣が腫大・肥厚・多嚢胞化することで卵胞の発育がスムーズに行われず、排卵が遅れてしまう病気です。
生理が不規則になったりニキビが増えたり、肥満傾向がある場合には、多嚢胞性卵巣症候群が疑われます。
多嚢胞性卵巣症候群の主な症状は以下の通りです。
- 思春期に月経が始まらず排卵がない
- 排卵が不規則に起こる
超音波検査で卵巣外側に10mm程度の卵胞が1列に並んでいる『ネックレスサイン』が確認できると、多嚢胞性卵巣症候群と診断されます。
月経異常の治療方法

月経異常の主な治療方法は以下の通りです。
- 鎮痛剤
- 低用量ピル
- ジエノゲスト(ディナゲスト)
- 漢方薬
- 原因となる病気の治療
ここでは上記3つの治療方法について解説します。
鎮痛剤
月経異常で起こる強い生理痛に対しては、鎮痛剤による治療が行われます。
正確には非ステロイド性抗炎症薬という治療薬で、内服薬、坐薬、注射薬などの種類があります。
非ステロイド性抗炎症薬は、生理痛の原因となるプロスタグランジンの産生に必要な酵素の働きを抑える作用があり、これによって生理時の腹痛や腰痛などの症状を和らげることが可能です。
鎮痛剤に加えて、子宮収縮を抑制する「ズファジラン」や「ブスコパン」といった薬を併用すると、より効果を高められます。
生理痛のつらい痛みにお悩みの方におすすめです。
低用量ピル
低用量ピルを服用することで、生理時の不快な症状を和らげられます。
低用量ピルには女性ホルモンが含まれており、このホルモンの働きによって生理痛の原因となるプロスタグランジンの分泌量を抑えられるのです。
低用量ピルは生理痛の緩和だけでなく、月経前症候群(PMS)や生理不順にも効果が期待できます。
避妊用ピル(OC)ではなく、生理痛や月経困難症の治療のためのピル(LEP)であれば保険適用となるため、月経異常に悩んでいる方は一度クリニックで相談してみましょう。
スマイルレディースクリニックでは、生理痛や月経困難症用の低用量ピル(LEP)としてルナベル、ジェミーナ、ヤーズを取り扱っています。
ジエノゲスト(ディナゲスト)
ジエノゲスト(ディナゲスト)は、黄体ホルモン単剤の治療薬です。
低用量ピルとは異なりエストロゲンが含まれないため、血栓症の副作用がありません。
ジエノゲストには1mgと0.5mgがあり、少ない方が低用量ピルで一番危険な血栓症の心配が無いため、最近処方例がどんどん増えています。
思春期世代である10代の方、40代の血栓症リスクが高い方にはこちらがファーストチョイスです。
漢方薬
自然由来の生薬を使用した漢方薬を服用することで、月経異常の症状を改善する効果が期待できます。
月経異常の治療で用いられる主な漢方薬は以下の通りです。
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 桃核承気湯(とうかくじょうきとう)
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
- 加味逍遙散(かみしょうようさん)
漢方薬による治療は、他の治療方法と比べると副作用が少ない特徴があります。
原因となる病気の治療
月経異常の原因が病気である場合、その病気の治療が必要です。
自覚症状がない場合も、隠れた病気の影響で月経異常が引き起こされている可能性があります。
月経異常がある場合はなるべく早めに病院を受診し、原因となっている病気がないか検査・診断してもらいましょう。
まとめ
月経異常は精神的・身体的ストレスによる女性ホルモンバランスの乱れによって引き起こされることが多いです。
しかし中には子宮筋腫や子宮内膜症、子宮腺筋症、卵巣腫瘍などの病気が原因となっていることもあります。
これらの病気は初期段階では自覚症状がない場合も多く、原因不明のまま放置しておくと、気づいたときにはかなり症状が進行してしまっていたというケースもあります。
月経不順や過多月経、無月経をはじめとした月経異常の症状が見られた場合には、自己判断して放置しておくのではなく、なるべく早めに婦人科を受診することが大切です。
スマイルレディースクリニックでは、患者様一人ひとりに対し適切な検査と診断のもと、痛み止め・LEP・ジエノゲスト・漢方薬など症状やご希望に合った治療薬を処方しています。
月経異常は日常生活に大きな影響を与えるだけでなく、将来の妊娠しやすさにも影響する問題です。月経異常にお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。