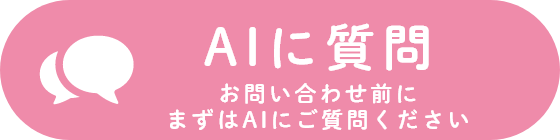月経周期や月経量、月経の持続期間、月経に伴う症状に異常が生じている状態を月経異常といいます。
月経異常は思春期や更年期などに起こりやすく、原因はホルモンバランスの乱れやストレス、生活習慣の乱れなどさまざまです。
この記事では、月経異常とはどのようなものなのか詳しく解説します。
正常な月経の状態や月経異常の症状、月経異常の診断・検査方法、治療方法などについてもまとめているため、月経異常の疑いがあり不安な方はぜひ参考にしてみてください。
正常な月経の状態

月経異常かどうか判断する前に、正常な月経の状態について知っておく必要があります。
正常な月経の状態には以下の4つの特徴があります。
- 月経周期が正常
- 月経の量が正常
- 月経の持続期間が正常
- 月経に伴う症状が強くない
ここでは上記4つの特徴についてそれぞれ解説します。
月経周期が正常
月経周期とは、月経が始まった日から次の月経が始まる日の前日までの期間の長さのこと。
その期間が25日〜38日の間に入っていれば、正常な月経周期といえます。
月経の量が正常
月経の経血量は、1回の生理中に20〜140mlの範囲内であれば正常です。
多い日でも2〜3時間に1回程度の頻度でナプキンを交換する程度であれば、正常と判断できるでしょう。
ただし経血の中にレバーのような塊が混じっている場合、経血量が多い可能性があります。
反対に経血量が極端に少ないことを過小月経といい、これも月経異常に分類されるため、少なすぎる経血量にも注意が必要です。
月経の持続期間が正常
月経の持続期間は3〜7日が正常な範囲です。
2日以内で終わってしまう場合や8日以上出血が続く場合は、何らかの原因が考えられます。
月経に伴う症状が強くない
月経に伴う症状として、腹痛、腰痛、頭痛などの症状がありますが、正常な月経であればこれらの症状は軽度で済みます。
日常生活に支障が出る程症状が強い場合、月経異常に分類される『月経困難症』の可能性が高いです。
月経異常にはさまざまな症状がある

月経異常にはさまざまな症状があり、以下のいずれかに分類されます。
- 月経困難症
- 月経不順
- 過多月経
- 無月経
- 月経前症候群(PMS)
- 月経前不快気分障害(PMDD)
ここでは上記の症状についてそれぞれ解説します。
月経困難症
日常生活に支障が出るほどの生理痛は『月経困難症』と呼ばれます。
月経困難症には『機能性月経困難症』と『器質性月経困難症』の2種類あり、それぞれ症状の原因が異なります。
| タイプ | 特徴 | 症状の原因 |
| 機能性月経困難症 | 身体に問題となる疾患がなくても現れる | 強い子宮の収縮 |
| 器質性月経困難症 | 身体にある疾患が原因で引き起こされる | 子宮内膜症や子宮腺筋症、子宮筋腫などの疾患 |
機能性月経困難症は思春期の女性に多く、器質性月経困難症は20代後半以降の女性に多いです。
機能性月経困難症
機能性月経困難症は、身体に問題となる疾患がなくても強い症状が現れるものです。
月経困難症と診断される人のうち、ほとんどがこちらに分類されます。
主な症状の原因は強い子宮の収縮によるもので、これによって強い腹痛が起こるほか、頭痛や嘔吐、下痢などを引き起こすこともあります。
器質性月経困難症
器質性月経困難症は、身体にある疾患が原因で強い症状が現れるものです。
原因となる疾患には以下のようなものがあります。
- 子宮内膜症:子宮内腔にある子宮内膜が卵巣や卵管などに発生してしまう疾患
- 子宮腺筋症:子宮内膜の組織が子宮の筋肉の中に入り込んでしまう疾患
- 子宮筋腫:子宮に腫瘍ができる疾患
上記のような疾患があると生理中の症状が強くなるだけでなく、生理中でなくても症状が現れることがあります。
月経不順
月経不順は月経周期に異常が生じている状態のことです。
月経周期の異常には頻発月経と希発月経の2種類あります。
- 頻発月経:月経周期が24日以内で頻度が多い
- 希発月経:月経周期が39日以上で頻度が少ない
月経不順が起こる主な原因は、ホルモンの分泌異常です。
ストレスやダイエットによる卵巣機能の乱れによって、ホルモンの分泌量に異常が生じることがあります。
過多月経
過多月経は、日常生活に支障が出る程に経血量が多い状態のことです。
通常の月経の経血量は多い日でも2〜3時間に1回程度の頻度でナプキンを交換する程度ですが、過多月経の場合は以下のような異常が生じます。
- 昼でも夜用ナプキンを使う日が3日以上ある
- ナプキン1枚では1時間も持たない
- 以前よりも月経量が増えた
過多月経による出血が多くなると、体内の鉄分が不足し『鉄欠乏性貧血』になることがあります。
鉄欠乏性貧血の主な症状は以下の通りです。
- 動悸や息切れ
- 倦怠感
- めまい
- 耳鳴り
- 頭痛など
過多月経が続くと徐々に鉄欠乏性貧血の症状が進みますが、貧血状態に体が慣れてしまうと症状を自覚できないこともあるため注意が必要です。
無月経
無月経は月経が来ない状態のことです。
『続発性無月経』と『原発性無月経』の2種類があり、それぞれの特徴と原因は以下の通りと考えられます。
| 種類 | 特徴 | 原因 |
| 続発性無月経 | 妊娠の可能性がないにもかかわらず、3か月以上月経が来ない状態 | 過度のストレスや無理なダイエット、下垂体腫瘍、排卵異常など |
| 原発性無月経 | 18歳になっても月経が来ない状態 | 染色体異常や子宮・卵巣の発育障害 |
無月経にはさまざまな原因があるため、診断や検査によって原因を特定し、その原因に合った治療が必要になります。
月経前症候群(PMS)
月経前症候群(PMS)は、月経が始まる3日〜10日前に身体的または精神的な不快症状が起こるものです。
女性ホルモンの一種であるプロゲステロンの増加が原因と考えられます。
症状の種類は200種類以上あるとされますが、代表的な症状は以下の通りです。
| 身体的症状の例 | 精神的症状の例 |
| 頭痛や偏頭痛腰痛便秘や下痢肌荒れ手足のむくみお腹の張り乳房の張りや痛み関節痛や筋肉痛など | イライラ抑うつ状態不安や緊張が高まる涙もろくなる集中力が低下する不眠や過眠など |
人によっては生活に支障が出るほど症状が強く出ることもあります。
月経前不快気分障害(PMDD)
月経前不快気分障害(PMDD)は、月経前症候群(PMS)の症状のうち、特に精神的な症状が悪化して起こるものです。
月経前3日〜10日になると感情のコントロールが難しくなり、抑うつや不安感、イライラなどの症状が強く出てしまいます。
月経が始まると症状はなくなるものの、精神状態が不安定になることによって人との衝突や摩擦が増え、社会活動に支障が出る場合もあります。
月経異常を放置しておくと不妊症になるリスクがある

月経異常を放置しておくと不妊症になるリスクがあります。
不妊症とは、何らかの原因によって自然妊娠する可能性がほとんどない状態のことです。
正確に言えば月経異常そのものが不妊症の原因になるのではなく、月経異常による無排卵状態が続くことで自然妊娠が妨げられます。
妊娠を考えている方は、早めに治療を受けることを検討しましょう。
月経異常の診断・検査方法

月経異常にはさまざまな症状があり、症状によって診断・検査方法が異なります。
例えば月経不順が疑われる場合、内診、超音波検査、血中のホルモン値の測定などを行うケースが多いです。
問診や血液検査によって原因が特定できることもあるため、内診や超音波検査に抵抗がある方は医師に相談してみましょう。
月経異常の治療方法

月経異常の治療方法は以下の通りです。
- 生活習慣の改善
- 低用量ピル
- ジエノゲスト(ディナゲスト)
- 漢方薬
- 鎮痛剤
- ホルモン療法
ここでは上記5つの治療方法についてそれぞれ解説します。
生活習慣の改善
生活習慣や体型が原因で月経異常が引き起こされている場合には、生活習慣の改善指導が行われます。
例えば月経不順の原因の一つに、肥満または痩せすぎが考えられるでしょう。
この場合はどちらの場合もBMI22〜23前後の適正体重に近づけるよう、食事や運動の指導が行われます。
また規則的な生活を送るのも月経異常の改善に大切なポイントです。
ストレスやホルモンバランスの乱れが原因となっている場合は、必要に応じてカウンセリングや認知行動療法などの治療が行われることもあります。
低用量ピル
女性ホルモンが含まれる低用量ピルを服用することで、生理痛の原因となるプロスタグランジンの増殖を抑えられます。
これによって腹痛や腰痛などの症状を緩和させることが可能です。
生理痛の緩和だけでなく、生理不順や排卵痛、ニキビの改善にも効果が期待できます。
低用量ピルにはさまざまな種類があり、自分の症状や体質に合ったものを選ぶことが大切です。
生理痛や月経困難症の治療用のピルは「LEP」と呼ばれ避妊用の「OC」とは区別されており、医師が治療に必要と判断した場合は保険適用でLEPが処方できます。
スマイルレディースクリニックではLEPとしてルナベル、ジェミーナ、ヤーズを取り扱っています。
ジエノゲスト(ディナゲスト)
つらい生理痛には、エストロゲンが含まれない黄体ホルモン単独のホルモン剤「ジエノゲスト(ディナゲスト)」も有効です。
ジエノゲストには1mgと0.5mgがあり、少ない方が低用量ピルで一番危険な血栓症の心配が無いことから、近年処方例がどんどん増えている薬です。
高い鎮痛効果があり、LEP(生理痛や月経困難症の治療用のピル)では十分な効果が得られない方にも選ばれています。
漢方薬
自然由来の生薬を使用した漢方薬を服用することで、月経異常に伴う不快な症状を和らげられます。
月経異常の治療に用いられる主な漢方薬は以下の通りです。
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)
- 加味逍遙散(かみしょうようさん)
検査を受けても身体に異常が見られないにもかかわらず、不快な症状が現れる場合に有効な治療方法です。
鎮痛剤
生理痛の症状が辛い場合、鎮痛剤で痛みを抑えることが可能です。
鎮痛剤には内服薬や坐薬、注射薬などの種類があります。
月経異常の治療に用いられる主な鎮痛剤の種類は以下の通りです。
- ロキソプロフェン
- アスピリン
- メフェナム酸
- イブプロフェン
- ジクロフェナク
- ナプロキセン
鎮痛剤は服用してから効果が現れるまでに時間がかかるため、痛みが出る前に服用するのが良いでしょう。
また、生理痛の治療に使われる「ズファジラン」「ブスコパン」との併用もおすすめです。
生理痛は子宮が収縮することで痛みが強くなりますが、これらの薬には子宮の運動を緩める作用があり、痛みの緩和に効果的です。
ホルモン療法
月経不順に対するホルモン療法(女性ホルモン製剤を用いた治療)としては、月経不順に対するホルモン療法の2種類があります。
| ホルムストローム療法 | カウフマン療法 | |
| 対象となる症状 | 黄体ホルモン分泌が起こらない月経異常 | エストロゲンと黄体ホルモンの両方の分泌が起こらない無月経 |
| 投与する女性ホルモン製剤 | 黄体ホルモン製剤 | エストロゲン製剤と黄体ホルモン製剤 |
| 治療方法 | 1.黄体ホルモン製剤を数日間投与する2.休薬して月経様の出血を起こす3.服薬と休薬を数か月周期的に繰返し、自然に排卵・月経が起こることを目指す | 1.エストロゲン製剤で子宮内膜を厚くする2.黄体ホルモン製剤を加えて排卵後の子宮内膜状況をつくる3.休薬して月経様の出血を起こす4.服薬と休薬を数か月周期的に繰返し、自然に排卵・月経が起こることを目指す |
どちらも女性ホルモン製剤を使用して、自然なホルモンの変化を疑似的につくることにより、自然に排卵・月経が起こることを目指す治療方法です。
まとめ
月経異常には月経困難症や月経不順、過多月経、無月経、月経前症候群(PMS)、月経前不快気分障害(PMDD)などの症状があり、それぞれ原因が異なる点に注意が必要です。
月経異常を改善するためには婦人科を受診し、専門医の診断のもと原因を特定することが大切です。
スマイルレディースクリニックでは、婦人科専門医が適切な検査と診断を行い、痛み止めや低用量ピルなどを処方しています。
月経異常に悩んでいる方は、ぜひ一度気軽にご相談ください。